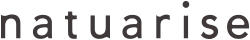最近、食中毒の原因ウイルスであるノロウイルスの感染が広がっています。実は、年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルスによるもので、そのうち70%ほどは11月〜2月に発生しているのだそうです。食中毒というと、夏に発生するイメージがあるので意外ですよね。  ちなみに国立感染症研究所によると、2025年第3週(1月13日〜1月19日)の感染者数は全国で「4.52」と、前の週に比べ「0.39増加」しています。2024年の第3週(1月15日〜1月21日)は「7.63」だったため昨年ほどではありませんが、油断はできません。
ちなみに国立感染症研究所によると、2025年第3週(1月13日〜1月19日)の感染者数は全国で「4.52」と、前の週に比べ「0.39増加」しています。2024年の第3週(1月15日〜1月21日)は「7.63」だったため昨年ほどではありませんが、油断はできません。
また感染者数が多い地域を都道府県別にみてみると、大分県(9.83)、石川県(8.14)、宮崎県(6.94)となっています。このエリアにお住まいの方は特に注意したほうがよさそうです。
ノロウイルスを予防するには、石けんと流水による手洗いが大切になります。消毒用エタノールもよさそうに感じますが、実はノロウイルスはエタノールが効きにくく、あくまでも補助的に使用するとよいといわれています。
ただ、エタノールは菌やウイルスだけでなく皮脂膜も奪ってしまうため、手荒れしやすいのが難点ですよね。
そこで見直されているのが、天然の抗菌物質として知られている植物由来の精油です。中世のヨーロッパでペストが大流行した際、なんと精油を扱っている香水工場で働く人だけが感染しなかったという記録が残っているのだそう。実際、多くの精油は、抗菌・抗ウイルス作用を持っていることが科学的に証明されています。
※画像はイメージ
ところが技術の発展によって抗生物質やワクチンなどが大量につくられるようになり、精油を用いた治療は徐々に衰退していきました。しかし近年では薬による副作用や薬剤耐性菌が出現していることから、精油を使った伝統的な療法が見直されはじめています。
たとえばユーカリやティートゥリーには抗菌・抗ウイルス作用があることがわかっているほか、ヒバという日本固有の木から抽出した精油にも黄色ブドウ球菌や大腸菌を減らす作用があることがわかっています。
<ヒバの抗菌作用に関する実験データはこちら>
また石川県農林総合研究センターによると、木材としてのヒバも、インフルエンザウイルスの感染性を止める働きがありそうだと発表しています。
精油は香りを楽しめるのもうれしいほか、嗅ぐと気持ちがリラックスするというメリットもあるなど、生活に取り入れることでいろいろ良いことがありそうです。