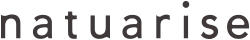ヒバの木は精油の原料になるので、そちらのイメージが強いという方もいらっしゃるかもしれませんが、実はヒバは木材として優秀で、伊勢神宮や弘前城など、いろいろな歴史的建造物に使用されているんです。
中でも、世界文化遺産に登録されている「中尊寺 金色堂」はヒバ材を用いた代表的な建物です。今回はそんな「中尊寺 金色堂」について、改めてみていきたいと思います。
▇中尊寺 金色堂の歴史
まず中尊寺というお寺は、平安時代前期である西暦850年に、円仁(えんにん)という僧侶によって開かれました。このときはまだ金色堂は建てられていません。
それから200年ほどの時を経て、「奥州藤原氏」が誕生します。奥州藤原氏は三代にわたって栄華を極めました。その初代当主である藤原清衡(きよひら)は、「前九年の役」「後三年の役」という大規模な戦で亡くなった人たちを供養するために、平安時代末期の1124年に金色堂を建立しました。
▇金色堂の見どころ①
金色に輝く阿弥陀堂
金色堂というだけあって、堂の内外には金箔が施されていて、荘厳な美しさを誇っています。それだけでなく、白く光る夜光貝の螺鈿細工(らでんざいく)や象牙、漆の蒔絵などの装飾品があり、お堂全体がまるで1つの美術館のようです。そのため、金色堂は「東日本随一の平安仏教美術の宝庫」とも呼ばれています。
▇金色堂の見どころ②
多すぎる仏像の数
お堂のなかにある須弥壇(しゅみだん)という台座の中心には阿弥陀如来が祀られていて、その両脇には観音勢至菩薩、六体の地蔵菩薩、持国天、増長天を従えています。こうした仏像の構成は、めずらしいのだそうです。そしてこの須弥壇のなかには、金色堂を造った清衡をはじめ、奥州藤原氏四代のお骨がいまも安置されています。
一度は聞いたことがあるであろう、中尊寺。改めてみてみると、いろいろな発見がありますね。
▇国宝がキレイに保存されていたのは、ヒバのおかげかもしれない
数々の見どころがある金色堂は、建物全体の93%(※)がヒバ材で造られています。ヒバの木は湿気のほか、虫や菌に対抗する力を持っており、金色堂が今もなお存在できているのは、ヒバの優れた材質のおかげといえるのではないでしょうか。
※出典:中尊寺ホームページ
▇ヒバに隠された驚くべきパワー
中尊寺を支えてきたと言っても過言ではないヒバ。そのおがくずから抽出したHIBA OIL(ヒバ精油)とHIBA WATER(ヒバ蒸留水)には、「消臭」「抗菌」「防虫」「リラクゼーション」という4つの機能があり、毎日のくらしをかなり快適にしてくれるんです。
なかでも人間が感知できる消臭作用には定評があり、「トイレのあとが気にならなくなった」「靴のニオイが消えた!」など、さまざまな声をお寄せいただいています。
そのすっきりとした消臭感は「中和消臭」に由来していて、ニオイを上書きするのではなく、中和して無臭化へと導いてくれるんです。
気になる方はぜひトップページをチェックしてみてくださいね。
▼Instagramでもいろいろな情報を発信中!